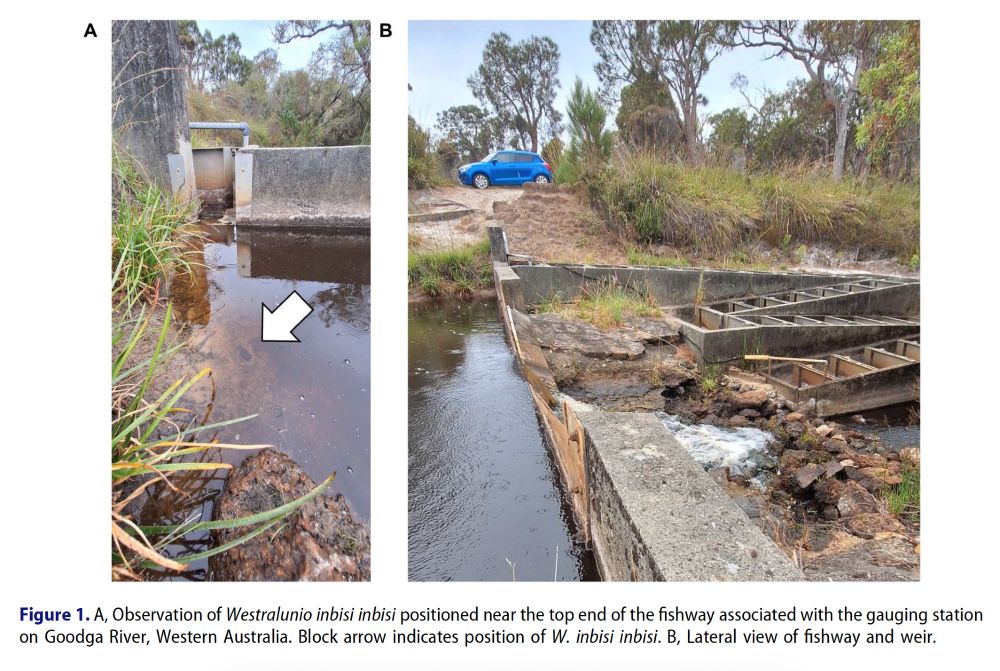𝘝𝘪𝘷𝘪𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘣𝘦𝘯𝘨𝘢𝘭𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Lamarck. — Küster, 1852: 17–18, no. 12, pl. 3, figs 14–16 (赤枠内).
Küster, H.C. 1852–1853. Die Gattungen 𝘗𝘢𝘭𝘶𝘥𝘪𝘯𝘢, 𝘏𝘺𝘥𝘳𝘰𝘤𝘦𝘯𝘢 und 𝘝𝘢𝘭𝘷𝘢𝘵𝘢. In Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. In: Küster, H.C. (Ed.), 𝘚𝘺𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘩𝘺𝘭𝘪𝘦𝘯-𝘊𝘢𝘣𝘪𝘯𝘦𝘵 𝘷𝘰𝘯 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯𝘪 𝘶𝘯𝘥 𝘊𝘩𝘦𝘮𝘯𝘪𝘵𝘻, Ersten (1) Bandes, einundzwanzigste (21) Abtheilung, 1–96, pls 1–14. Bauer & Raspe, Nürnberg (pp. 1–56 and pls 1–8 in 1852, pp. 57–96 and pls 9–14 in 1853).
https://www.biodiversitylibrary.org/page/34226377
https://www.biodiversitylibrary.org/page/34226803
MR新着。バングラデシュでオニテナガエビ 𝘔𝘢𝘤𝘳𝘰𝘣𝘳𝘢𝘤𝘩𝘪𝘶𝘮 𝘳𝘰𝘴𝘦𝘯𝘣𝘦𝘳𝘨𝘪𝘪 (De Man 1879) 養殖場の余剰有機物除去と水質改善に役立ちそうな在来の淡水産貝類を検討。タニシ科の 𝘽𝙚𝙡𝙡𝙖𝙢𝙮𝙖 𝙗𝙚𝙣𝙜𝙖𝙡𝙚𝙣𝙨𝙞𝙨 (Lamarck, 1822) が濾過摂食を行うことや旺盛な繁殖力から最有力候補として浮上。
doi.org/10.1080/1323...
この養殖場は温室効果ガスを多く排出し、環境への悪影響が問題視されているので、その軽減に貝類を利用したいようです。タニシ科の種は確かに使い勝手がよいかもしれません。候補種は美しい殻をもつ種です。
06.02.2026 11:24 — 👍 10 🔁 5 💬 0 📌 0

Bartsch, P. 1936 (11 May). Molluscan intermediate hosts of the Asiatic blood fluke, 𝘚𝘤𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘴𝘰𝘮𝘢 𝘫𝘢𝘱𝘰𝘯𝘪𝘤𝘶𝘮, and species confused with them. 𝘚𝘮𝘪𝘵𝘩𝘴𝘰𝘯𝘪𝘢𝘯 𝘔𝘪𝘴𝘤𝘦𝘭𝘭𝘢𝘯𝘦𝘰𝘶𝘴 𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴, 𝟵𝟱(5)(3384): 1–60, pls 1–8.
https://www.biodiversitylibrary.org/page/24739421
MR新着。日本住血吸虫を媒介する中国産ミゾヒダニナ(日本のミヤイリガイの別亜種)の新たな駆除剤として、アオカビ属の一種 𝘗𝘦𝘯𝘪𝘤𝘪𝘭𝘭𝘪𝘶𝘮 𝘢𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘰𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘶𝘮 Z12株の有効性を検証。その酢酸エチル抽出物とn-ブタノール抽出物は、ミゾヒダニナの中腸腺での蛋白質合成を阻害し個体を死に至らしめたことから、駆除成分が濃縮されていると見做しうる。
doi.org/10.1080/1323...
(画像は今回の論文のものではありません。Bartsch (1936) によるミゾヒダニナとその近縁種群:figs 1, 4 がミヤイリガイ、17 が狭義のミゾヒダニナ)
10.01.2026 11:24 — 👍 10 🔁 2 💬 0 📌 0

𝙋𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖𝙙𝙞𝙖 cf. 𝙨𝙪𝙗𝙪𝙡𝙖𝙩𝙖 collected in the Okinawa Islands, Japan. A, Live specimen NSMT-Mo 79665 from Seragaki, 3.3 mm in shell length, apertural, lateral, and abapertural views. Greyish and yellowish soft parts visible through shell. B, Empty shell of young individual NSMT-Mo 79666 from Seragaki, 2.0 mm, apertural view. C, Empty shell in ST’s personal collection from Seragaki, 3.5 mm, apertural and abapertural views. D, Live specimen MPM. Coll. No. 25372 from Ie-jima Is., 3.2 mm, apertural, lateral, and abapertural views. Shell destroyed after taking photographs for molecular analysis. E, Close-up view of protoconch of MPM. Coll. No. 25372. Arrows denote demarcation line with teleoconch. F, G, Live-taken photographs of MPM Coll. No. 25372. Scale bars = 1 mm (A–D) and 0.2 mm (E).

MR新着。従来死殻のみ知られていた、奇抜な形の 𝙋𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖𝙙𝙞𝙖 Laseron, 1956 の生貝(クモヒトデ類に一時的に寄生する可能性あり)による再検討。分子系統樹ではハナゴウナ科の 𝘗𝘺𝘳𝘢𝘮𝘪𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰𝘪𝘥𝘦𝘴 レイシツボ属, 𝘌𝘶𝘭𝘪𝘮𝘢 ハナゴウナ属, 𝘏𝘦𝘮𝘪𝘭𝘪𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘤𝘢 クテンハナゴウナ属等と単系統群を形成した。
doi.org/10.1080/1323...
高野剛史氏らによる著作。この属がレイシツボ属に近縁というのは、殻の類似性から納得です。今回の検討標本の多くは海底洞窟・珊瑚礁間隙の底質・珊瑚下面から採取されており、この属は隠蔽環境を好むらしいとのこと。
06.01.2026 09:24 — 👍 11 🔁 3 💬 0 📌 1

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
「ウマ」を名に冠する貝類は少ないので、他の方とも被ると思いますがウマノサワラビを挙げます。このウマ(午)は、画像右の天狗生(=吉良哲明)氏の解説にある通り、南の方角(に分布する)という意味です。「子午線」は北(ネズミ)と南を結ぶ線というわけですね。
ウマノサワラビには画像中央下部に挙げた個体(異名のタイプ標本)のごとく、巻きが解ける個体が現れるとされています。『原色世界貝類図鑑II 熱帯太平洋編』に同様の個体が載っているを子供の頃に見て以来、ずっと憧れなのですが、いまだ実物に接する幸運に恵まれません。
01.01.2026 01:45 — 👍 32 🔁 12 💬 0 📌 0
物体の大きさや文献の頁数など数値の幅は、ハイフン(-)よりenダッシュ(–)を用いるのが適切で、大半の活字刊行物は両者を区別していますが、その差異を認識して自らの原稿に反映させている人は非常に少なく感じます。こうした形式がいい加減だと、内容の信頼度や受理の可否に影響する惧れもあります。
画像下部の「間違い探し」における形式の誤り(全部で11箇所)の説明はALTに書き込みました。
26.12.2025 11:24 — 👍 13 🔁 8 💬 0 📌 1
最優秀賞を射止めた佐藤宏樹氏の発表に対する銓衡委員の選評は:
多留副会長「パワポの見せ方や話し方という点においてダントツ」
芳賀前会長「抜群」「生き生きとしていて、なにより楽しそうで、輝いていた」
福田「ぶっちぎりで突出」「パワポの完成度が著しく高く、洗練されていた」
などなど。
発表の審査においては、私は内容や話し方に加えてパワポの表記・構成も重視しています。学名の用法が不適切なのは論外なので大幅に減点し、さらに画像2枚目に挙げた各記号の扱いなども評価対象とします。スペースやカンマ等の置き方が適切な学生発表はごく稀ですが、今回の佐藤氏の発表はこの点が完璧でした。
25.12.2025 11:24 — 👍 8 🔁 3 💬 0 📌 1
3日前に新種記載されたセキガハラゴマオカチグサや、その翌日に公表されたシロスソカケなどスカシガイ科のホモニム問題に絡む各学名の新規追加・変更も、早くもMolluscaBaseに一通り反映されました。昨晩ブシェ博士から「論文のpdfをくれ」とメールが来たので、送ったらすぐに対応してくれました。彼は今米国出張中とのことですが、出先でも欠かさずデータベース入力や訂正を続けているようです。
doi.org/10.1080/1323...
doi.org/10.1080/1323...
21.12.2025 11:24 — 👍 2 🔁 1 💬 0 📌 0

MR新着。温暖化が住血吸虫症を媒介する貝類に与える影響。宿主となる貝類は生存に最適な温度範囲が種ごとに異なるため、気候変動は繁殖や分布の変化に直結し、住血吸虫の発育と疾患伝播の動態にも影響を与える。感染伝播域が拡大するだけでなくその移動をも促す可能性がある。
doi.org/10.1080/1323...
この総説で議論の対象とされているのはヒラマキガイ科の 𝘉𝘪𝘰𝘮𝘱𝘩𝘢𝘭𝘢𝘳𝘪𝘢 とマンソン住血吸虫、同科の 𝘉𝘶𝘭𝘪𝘯𝘶𝘴 とビルハルツ住血吸虫、およびミヤイリガイを含むイツマデガイ科ミゾヒダニナ属 𝘖𝘯𝘤𝘰𝘮𝘦𝘭𝘢𝘯𝘪𝘢 と日本住血吸虫です。
21.12.2025 09:42 — 👍 3 🔁 4 💬 0 📌 0

日本では 𝘼𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙖 Albers, 1850 オオベソマイマイ属(ケマイマイ類)の新参異名と見做されてもはや使う人も少ない 𝙏𝙧𝙞𝙨𝙝𝙤𝙥𝙡𝙞𝙩𝙖 Jacobi, 1898 オトメマイマイ属(シロマイマイ類)が、数日前にようやく MolluscaBase でも無効名扱いに修正されました。
先月発表した Fukuda & Hirano (2025) での扱いを踏まえています:
doi.org/10.1080/1323...
21.12.2025 09:24 — 👍 6 🔁 2 💬 0 📌 1
今回のホモニム迷宮論文は、室内に籠って文献検索するだけで書き上げた「こたつ記事」ですが、結果として実物を見たこともないチリ産の種に新たな学名を与えることになるとは、さすがに予想外でした。
私は常々冗談で「世の中に背を向けて引き籠り、俯いて足許を垂直にとことん掘りまくれば、いずれ眼前には南米大陸の青い空と海とが広がるはず、地球は丸いのだから」と言っていたのが、半ば冗談で済まなくなってしまいました。
荒ぶる自然や世間の喧騒から距離を置いて密室に立て篭もることで、初めて真理が見えてくることも確かにあるようです。
doi.org/10.1080/1323...
20.12.2025 13:22 — 👍 3 🔁 1 💬 0 📌 0

𝘈𝘤𝘩𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘪𝘮𝘮𝘢𝘤𝘶𝘭𝘢𝘵𝘢 Lamarck, 1822. — Deshayes in Férussac, 1851 (30 Jul.): vol. 2, 158, pl. 127, figs 1–2.
Férussac, A.E.J.P.F. d’Audebard de 1819–1832. 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘨é𝘯é𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘪è𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘭𝘭𝘶𝘴𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘧𝘭𝘶𝘷𝘪𝘢𝘵𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘦𝘴𝘱è𝘤𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘭’𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘶𝘷𝘦 𝘢𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘥’𝘩𝘶𝘪 𝘷𝘪𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴, 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘥é𝘱𝘰𝘶𝘪𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘯’𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘭𝘶𝘴; 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴é𝘴 𝘥’𝘢𝘱𝘳è𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵è𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘭𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘳é𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘶𝘹 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘤𝘰𝘲𝘶𝘪𝘭𝘭𝘦𝘴. Tome deuxième, première partie. J.-B. Baillière, Paris.
https://www.biodiversitylibrary.org/page/52470202
https://www.biodiversitylibrary.org/page/52686239

MR新着。中国海南島にはアフリカマイマイ 𝘓𝘪𝘴𝘴𝘢𝘤𝘩𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘧𝘶𝘭𝘪𝘤𝘢 (Bowdich, 1822) に加えて同属の別種 𝘓. 𝘪𝘮𝘮𝘢𝘤𝘶𝘭𝘢𝘵𝘢 (Lamarck, 1822) も移入されている。両種の拡大動態をCOI遺伝子で調べたところ、後種は検討個体数の82%を占めた一方で遺伝的多様性は小さいという。
doi.org/10.1080/1323...
日本ではアフリカマイマイは1種しか知られていないので、近縁な別種(殻はなかなか壮麗)が海南島に侵入し、蔓延しているとは驚きです。しかも個体数が圧倒的。島内での遺伝的多様性の低さを見ると、移入機会はまださほど多くないようですが。
19.12.2025 11:24 — 👍 5 🔁 1 💬 0 📌 0

MR新着。オオオカチョウジ 𝘈𝘭𝘭𝘰𝘱𝘦𝘢𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘤𝘪𝘭𝘦 (Hutton, 1834) が、インド産 𝘗𝘵𝘦𝘳𝘰𝘤𝘺𝘤𝘭𝘰𝘴 𝘳𝘶𝘱𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘴 Benson, 1832(ヤマタニシ科)の腐肉と殻を摂食する様子を観察。周囲に他の餌資源が豊富に存在していても屍貝に群がって貪り喰うという。
doi.org/10.1080/1323...
類似した現象は日本産の陸貝でも時々見られるので、特に驚きはありませんが、活字で明確に報告された例は少ないかもしれません。
12.12.2025 09:44 — 👍 10 🔁 2 💬 0 📌 0

沖縄本島で姿消すカタツムリ いったい何が… | NHKニュース
【NHK】沖縄は日本全体のカタツムリの約20%の種類が生息し、そのほとんどが固有種といういわばカタツムリの「楽園」です。しかし、沖縄本島では今、絶滅危惧種が急速に姿を消し、国や県が保護に乗り出す事態になっていま
沖縄島に固有の陸産貝類の危機的状況、特に国内外来種ヤエヤママドボタルによる捕食の脅威を報じたNHKのニュース特集。螢探知犬の活躍や、もはや風前の灯火に追い詰められたアマノヤマタカマイマイとその保全対策などにも言及されており、充実した内容です。
これらの内容の一部は、番組中でコメントされている久保弘文元会長ご自身が、明後日(13日)の当会大会で詳しく発表されます。
news.web.nhk/newsweb/na/n...
11.12.2025 09:42 — 👍 24 🔁 9 💬 0 📌 0
今週末(13・14日)開催予定の当会大会について、東日新聞で記事に取り上げていただきました。世話役の西さんから発出された丁寧なプレスリリースに基づいています。西さんならびに記者の方、ありがとうございます。
豊富な貝類標本 研究利用拡大に期待 | 東日新聞
www.tonichi.net/news/index.p...
10.12.2025 09:17 — 👍 11 🔁 5 💬 0 📌 0
来たる13・14日の当会大会には多数の参加申込を戴きありがとうございます。両日のプログラムが確定しました(同じものは当会HPでも明日公開予定です)。
13日は13時受付開始で、研究発表ののち15時半から博物館の収蔵庫見学、その後に懇親会です。
14日は9時半受付開始、研究発表後半を経て15時からは柏尾翔会員による普及講演会です。
皆様にお会いできるのを心待ちにしています!
07.12.2025 09:33 — 👍 5 🔁 2 💬 0 📌 1

MR新着。ブラジル・サンパウロ州のJuréia-Itatins Mosaic保護区に侵入した貝類の外来種3種(海産のミドリイガイ・イガイダマシおよび淡水産のヌノメカワニナ)の現状と在来生態系への影響を考察。いずれも日本を含む世界中に移入されている種ながら、この地域での詳細な研究例は少なかった。
doi.org/10.1080/1323...
これまでアジアなど太平洋沿岸諸国でよく知られていた移入種の貝類が、近年は南米大西洋岸にも飛び火して急速に広がりつつあり、この3種以外にもまだ認識が不十分なものが既に多数定着している可能性が大です。
06.12.2025 12:36 — 👍 3 🔁 1 💬 0 📌 0
![岡山県児島郡琴浦町瑜伽[現・倉敷市児島由加].
畠田和一コレクション #4838.殻長6.2 mm,殻径9.2 mm.](https://cdn.bsky.app/img/feed_thumbnail/plain/did:plc:gznyu7wc5z5ftjygtte36km3/bafkreibncgcuu56ojh6gpjmyba5j3wpvlz54zpa2usyk6xsidbwzfqapnm@jpeg)
岡山県児島郡琴浦町瑜伽[現・倉敷市児島由加].
畠田和一コレクション #4838.殻長6.2 mm,殻径9.2 mm.

岡山県RDB2020動物編, p. 519.
![岩崎敬二・石田 惣・柏尾 翔・亀田勇一・久保弘文・齊藤 匠・澤田直人・芳賀拓真・早瀬善正・平野尚浩・福田 宏 2025 (31 Aug.). 日本産軟体動物の稀少な未記載種の形態的標徴, 分布ならびに棲息環境. 𝘔𝘰𝘭𝘭𝘶𝘴𝘤𝘢𝘯 𝘋𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺, 𝟳: 93–210 [177–178].](https://cdn.bsky.app/img/feed_thumbnail/plain/did:plc:gznyu7wc5z5ftjygtte36km3/bafkreicxxgs55qgxxa7wwmi5xvxzpk75gsthyj3evxcmzecj764dvcg67i@jpeg)
岩崎敬二・石田 惣・柏尾 翔・亀田勇一・久保弘文・齊藤 匠・澤田直人・芳賀拓真・早瀬善正・平野尚浩・福田 宏 2025 (31 Aug.). 日本産軟体動物の稀少な未記載種の形態的標徴, 分布ならびに棲息環境. 𝘔𝘰𝘭𝘭𝘶𝘴𝘤𝘢𝘯 𝘋𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺, 𝟳: 93–210 [177–178].
MR新着。アワジオトメマイマイに新名 𝘼𝙚𝙜𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙖𝙬𝙖𝙟𝙞𝙤𝙩𝙤𝙢𝙚 Fukuda & Hirano を提唱。
doi.org/10.1080/1323...
従来の学名 𝘛𝘳𝘪𝘴𝘩𝘰𝘱𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘢𝘸𝘢𝘫𝘪𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Pilsbry, 1901 は、𝘛𝘳𝘪𝘴𝘩𝘰𝘱𝘭𝘪𝘵𝘢 Jacobi, 1898 が 𝘈𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘢 Albers, 1850 の異名とされた結果、𝘈. 𝘢𝘸𝘢𝘫𝘪𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 (Gude, 1900) ジタロウマイマイの新参二次同名となり、有効な学名がない状態だったのでこのたび解決しました。詳しくは画像2・3枚目の岡山県RDB2020と岩崎他, 2025をごらんください。
12.11.2025 11:35 — 👍 7 🔁 4 💬 0 📌 0


MR新着。豪州固有種 𝙋𝙚𝙡𝙨𝙚𝙣𝙚𝙚𝙧𝙞𝙖 𝙗𝙧𝙪𝙣𝙣𝙚𝙖 (Tate, 1887)(日本のダニガイと同属)が宿主の 𝘏𝘦𝘭𝘪𝘰𝘤𝘪𝘥𝘢𝘳𝘪𝘴 𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢 (Valenciennes, 1846)(ムラサキウニと同属)の背面に、稚貝が多数蠢く卵塊を産み付ける様子を初めて動画で記録。
doi.org/10.1080/1323...
動画をここでご披露できないのが残念です。論文表題は「千の言葉以上の価値がある」で始まり、動画には著者の「実況」が録音されていて楽しい仕上がりです。ウニに産み付けられた卵嚢の数の多さに加え、その1個1個の中でくるくる回る稚貝が想像以上に大勢で驚き。
14.10.2025 11:24 — 👍 10 🔁 2 💬 0 📌 0
後篇が公開されました! 前篇には多くの反響を賜りありがとうございました。
後篇には前篇にもまして多彩な情報を盛り込みましたので、よろしくお願い申し上げます。文中で触れている『鑑識眼の科学』は名作です。
note.com/yamakei90_/n...
13.10.2025 06:14 — 👍 16 🔁 7 💬 0 📌 1

MR新着。ベトナムでドラゴンフルーツを食害し、枝や果実へ甚大な被害を与えるタママイマイ 𝘼𝙘𝙪𝙨𝙩𝙖 𝙩𝙤𝙪𝙧𝙖𝙣𝙣𝙚𝙣𝙨𝙞𝙨 (Souleyet, 1842) の、綜合的害虫管理に向けた繁殖生態の把握。
最も繁殖するのは気温が25℃の時ながら、広い範囲の温度で高い孵化率を示した(つまり、気温が多少変動しても繁殖力はさほど低下しない)。混合餌を与えるとドラゴンフルーツ単独よりも繁殖力がより高まり、孵化期間も短縮する。
農地での個体群密度のピークは、水分と植生が最も豊富に存在する乾季から雨季への移行期である。
doi.org/10.1080/1323...
10.10.2025 11:46 — 👍 5 🔁 2 💬 0 📌 0
MR新着。ベンガルヌマガイを用いての淡水真珠養殖において、真珠の品質と宿主の生存率向上をともに追求した続報。ポリ-D-リジンの効果を論じた前回の論文(RP)と同じく、インド・アッサム地方の研究チームによる著作です。
doi.org/10.1080/1323...
今回は水素化ケイ素(シラン silane)でコートした核を用いると、 宿主の生体への適合性・生存率および真珠の質(光沢と滑らかさ)のいずれにも劇的な効果があると実証。
画像4枚目のFigs 29, 30を見ると、シラン不使用(29)と使用したもの(30)とでは光沢の強さが確かに全く異なり、ここまで顕著な差が生じるとは驚きです。
07.10.2025 11:24 — 👍 5 🔁 2 💬 0 📌 0
寄生虫学分野の大学教員。特に住血吸虫をメインに研究を行っています。掲載している動画・写真は私が個人で撮影したものです。営利目的での無断使用はお断りします。教育教材で使う場合は許可はいりませんが、出典を載せてください。私信につき所属機関を代表する意見ではありません。
絵や図表を作るコミュ障、独特な鋏角類やラディオドンタ類を嗜む節足動物厨
Introvert illustrator and arthropod enjoyer. Mainly fond of unique chelicerates and radiodonts.
詳細/Details:http://twpf.jp/ni075
squid-driven creature
イカがすきなもの
イカと色々のアカウント
ほぼ同じIDでついったとインスタにもいます。
画像動画等無断利用やめてね No unauthorized use.
Senior lecturer @ Uni Malaysia Sabah 🇲🇾
Biodiversity, ecology, freshwater molluscs & other inverts, invasive species, natural history collections, Southeast Asia
she/her
https://orcid.org/0000-0002-5123-0039
ヤスデの人 millipede
解剖と謎解きが好き
Founded in 1893. Dedicated to the advancement of research & education on molluscs.
https://malacsoc.org.uk/
The MSA is dedicated to the appreciation, conservation and celebration of molluscs. To get more involved in the wonderful world of molluscan research check out www.malsocaus.org
現代美術家 保存の民
日々の観察と記憶のめも用
https://mitou-motoko.com/
生き物のイラストと本をかいています。『僕らが死体を拾うわけ』『冬虫夏草ハンドブック』『琉球植物民俗事典』『生き物の描き方』『土をつくる生き物たち』『調べてびっくり! テントウムシ』『マイマイは美味いか』『めんそーれ!化学』などなど。
PhD丨Biologist/paleontologist studying 🐌 & 🐦丨Dungeon Master丨Curator & researcher at @nathist.bsky.social, @helsinki.fi丨Editor of the Journal of Geek Studies (@jgeekstudies.bsky.social)丨🇧🇷 🇩🇪 🇳🇿 🇳🇴 🇫🇮
軽井沢町花サクラソウをシンボルとして、生物多様性をより豊かにして次世代に引き継ぐために活動しています。https://sakuraso.org/
▽Japanese sculpture/ 造型
▽Snail
『世界のかたつむり』名義で、陸貝の造形をしたり、眠っていたり。たまに仕事の事。
カタツムリから学ぶスローライフ🎓『こつむ日記』執筆中🐌カタツムリの暮らしを中心に、生態や雑学、その他お役立ち情報を掲載しています😊
【カタツムリのブログ】
https://kotsumu.com/
【カタツムリのZINE・こつむ舎】
https://kotsumu.base.shop/
特撮、映画、MOTHER2
たまに深夜の馬鹿力。
第11回ネット小説大賞受賞作
【怪奇話集 タクシー運転手のヨシダさん】
発売中!
ネット通販
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784299057167
または最寄りの本屋さんで是非!
ご連絡は
kazuya18@hotmail.co.jp
までどうぞ。
カタツムリが好きです。Xのりんたろうです。Xに投稿したものなどを再度投稿いたします。
晴耕雨読の団栗/最近はGeminiに提案させた参考図書をたどりつつ、ニーチェを理解しようとしてます。でも寄り道したカントが面白い。(栗鼠は冬眠しています)
a PD fellow in the isolated jungle island of the Ryukyus
Deep-sea biologist / Malacologist @JAMSTEC and @Senckenberg. Chemosynthesis-based ecosystems. 海洋生物学者・深海・軟体動物・化学合成生態系。
Website: https://squamiferum.net
See the collection: https://www.conchology.be/?t=92






























![岡山県児島郡琴浦町瑜伽[現・倉敷市児島由加].
畠田和一コレクション #4838.殻長6.2 mm,殻径9.2 mm.](https://cdn.bsky.app/img/feed_thumbnail/plain/did:plc:gznyu7wc5z5ftjygtte36km3/bafkreibncgcuu56ojh6gpjmyba5j3wpvlz54zpa2usyk6xsidbwzfqapnm@jpeg)

![岩崎敬二・石田 惣・柏尾 翔・亀田勇一・久保弘文・齊藤 匠・澤田直人・芳賀拓真・早瀬善正・平野尚浩・福田 宏 2025 (31 Aug.). 日本産軟体動物の稀少な未記載種の形態的標徴, 分布ならびに棲息環境. 𝘔𝘰𝘭𝘭𝘶𝘴𝘤𝘢𝘯 𝘋𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺, 𝟳: 93–210 [177–178].](https://cdn.bsky.app/img/feed_thumbnail/plain/did:plc:gznyu7wc5z5ftjygtte36km3/bafkreicxxgs55qgxxa7wwmi5xvxzpk75gsthyj3evxcmzecj764dvcg67i@jpeg)