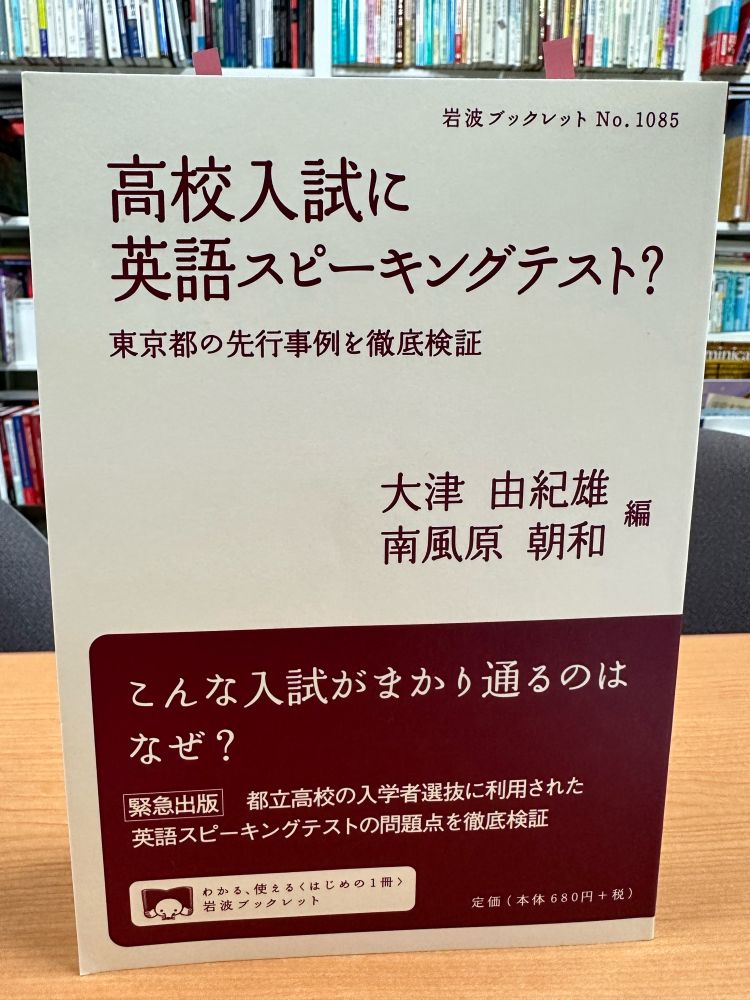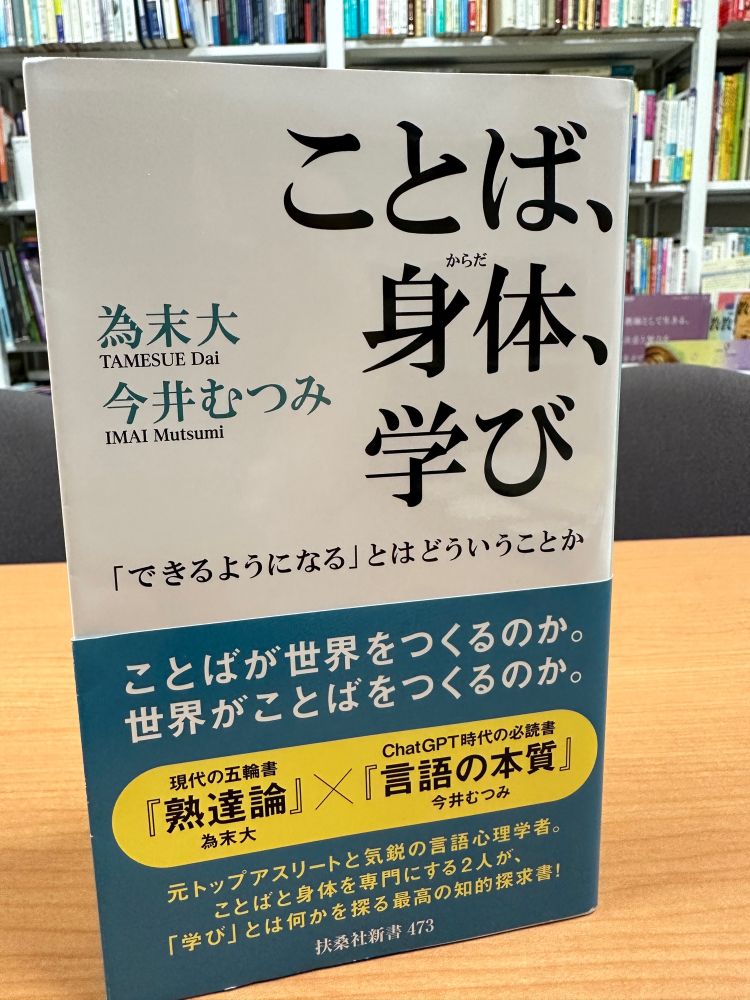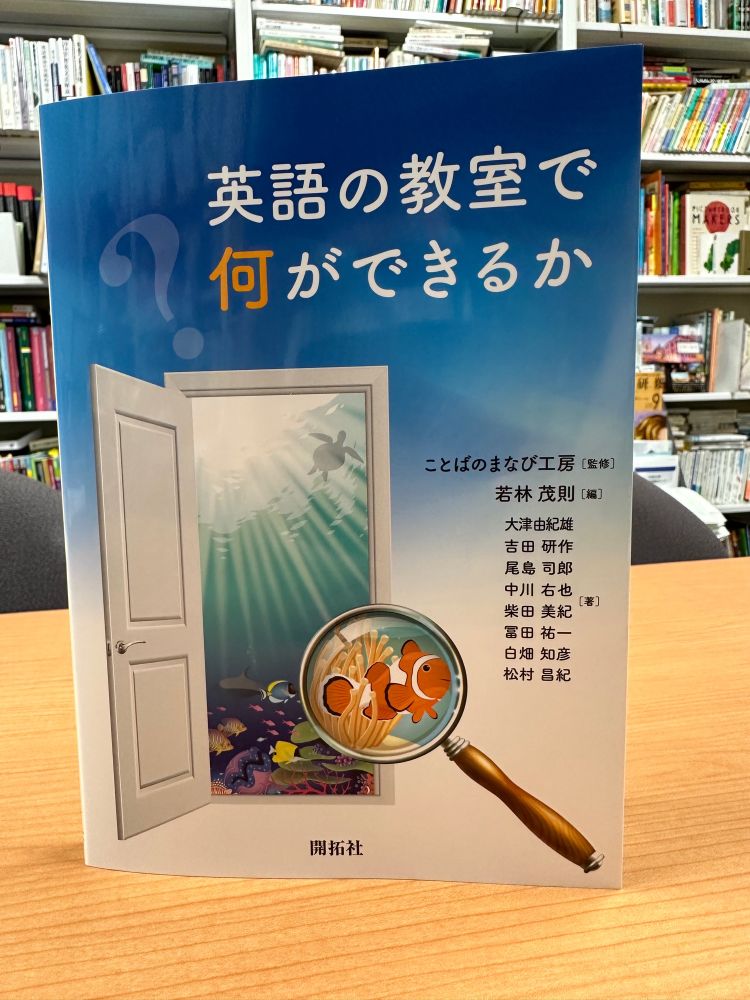こういう指摘を、『英語教育』誌その他で、テスティングを専門とする英語教育関係者、あるいは都の中等教育に関わる研究者が指摘したことはあっただろうか。大学入試への外部試験問題のときに既に一度、英語教育関係者の大半は私の中で死んだが、学校英語教育が滅ぶまで死に続けるのかもしれない。
>大津由紀雄・南風原朝和(編)『高校入試に英語スピーキングテスト?: 東京都の先行事例を徹底検証』岩波書店. amzn.to/3SPbwR4
28.11.2023 02:32 — 👍 1 🔁 1 💬 0 📌 0
例えば「このように、制度的にESAT-Jを不受験となってしまう生徒がいて、それらの受験者に対する措置において、事前に予測できるような系統的な誤差が生じることは、入学者選抜の方法として公平性に欠けると言わざるを得ません。いわば、制度に組み込まれた不公平が存在することになります」(p. 26) とか「また、たとえば79点と65点は段階別評価ではともにBとなり、数値換算では同じ16点となります。それなりに時間をかけて実施し、採点して得られた得点差をこのようにつぶすことは、テスト結果の持つ情報量をみすみす捨てることになり、コストの無駄遣い以外の何ものでもありません」(p. 29)とか。
28.11.2023 02:31 — 👍 1 🔁 1 💬 1 📌 0
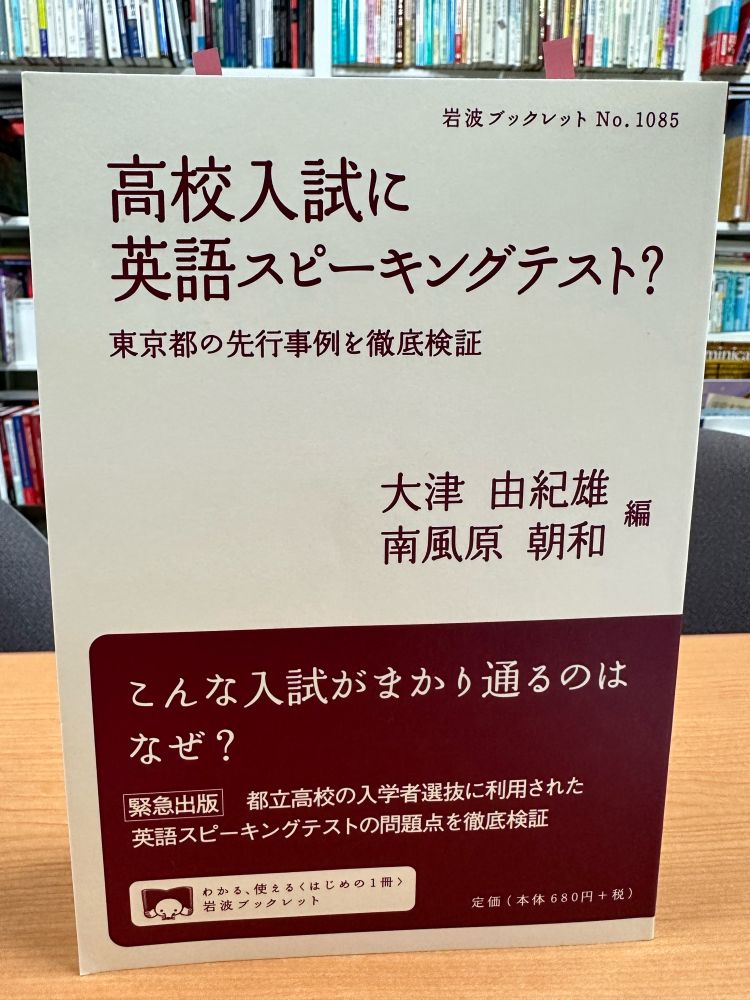
私自身も含めWebやSNS上で散々議論してきたことなので、いまさら書籍?と思うところもあったが、実に必要な一冊だった。問題が端的かつ切実に整理されている。
特に英語教育関係者以外に、コトの経緯と問題の確信を伝えるのに本書はうってつけだ。どの章もだいじだが、南風原先生と羽藤先生の章は特に刺さる。
28.11.2023 02:31 — 👍 6 🔁 3 💬 1 📌 0
(3) コンパクトながら重要な人物や概念、史実が網羅されている。その柔らかくも大事なところを逃さない語りに感心しきり。資料も豊富で、特に学校と社会の歴史の第2部がアツい。細切れの教採対策本で勉強するぐらいなら、授業のテキストでなくとも本書を読んだほうが良い。
(4) ただし、Further Readingsの文献の難易度はまちまちでキュレーションが必要。細かい所で、言語教育の立場から言えば、第13章の「翻訳アプリを使えば、言語の壁を超えた協働も可能です」(p. 219)というのは単純化し過ぎというか、言葉足らずだなと思うけども。
とにかくいい仕事!
25.10.2023 14:37 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
(1) コンパクトな記述に即して「文献にチャレンジ」に挙げられた文献の的確さ。著者たちの造詣の深さに起因するのだろうが、最新のものまで含めて、ハズレのない選りすぐりの文献が並ぶ。これを追っかけて読んでいくだけで良い教育学者が育ちそう。
(2) 構成の巧みさ。章の扉のQuizで初学者の関心を引き、節内の問いで深く考えさせる。冒頭で関連する章を図解し、章をまたぐクロスリファレンスや言及も豊富。教育学の授業の担当者が全ての領域に研究レベルで詳しいことも稀だろうが、本書を通じて参考文献に当たっていけば良い授業ができるだろう。
25.10.2023 14:37 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0

読了。時間があれば改めてレビューしたいが、こんな教育学(概説)のテキスト、とっても素敵で、本当に「これからの」やんという感じ。四半世紀前に本書を通じて教育学を学んでいたら、どうなっていただろうか。
>神代健彦・後藤篤・横井夏子 (2023). 『これからの教育学』有斐閣. amzn.to/3s9dhgP
25.10.2023 14:37 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

これは学生に薦められる良書。企画・構成が良い。対象レベル的に、ライティング指導を扱う授業の中で掘り下げて扱うことはできないが…(エッセンスは大井『「英語モード」でライティング』などをもとに伝えているつもりだけれども)。
>成田 あゆみ (2023).『新しい英文ライティングの実践力』DHC. amzn.to/3QyaZkV
25.10.2023 14:35 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
ブログ更新: 亘理研究室 ver 3.0|[レビュー076] 八田・渡邉『高等学校 観点別評価入門』 www.watariyoichi.net/wp-admin/pos...
18.10.2023 13:38 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0

そんなにあれこれ見ているわけではないが、これは先生方に薦められる。いま一冊手に取るならこの本じゃないかな。
>福原将之(2023).『教師のためのChatGPT入門』明治図書. amzn.to/3PE6Utw
29.09.2023 13:53 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0

神代健彦さん(京都教育大)にご恵投いただきました。ありがとうございます!拝読するのが楽しみです。来年度以降のゼミ・授業文献候補が増えて、嬉しい悩み。
>神代健彦・後藤篤・横井夏子(2023). 『これからの教育学』有斐閣. amzn.to/48qtfDx
22.09.2023 04:16 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
前に日本教育学会で、英語教育に巣食うパーフェクショニズムが桎梏となってるよ的発表をした際、それはどちらかといえば各個人の実存主義的言語観の内にある課題を指摘するもので、本質主義的側面にはあまり目配せをしていなかったことに気づいた。英会話学校の広告に代表されるような形で現出する「母語話者主義」は、authenticityの本質主義的概念の側に根差している。母語話者を至上の存在として、完璧な言語の使い手でない限り自らは劣った存在だと考える言語(教育・学習・使用)観を脱却するためには、こちらも見なければならないんだな。
13.09.2023 15:30 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
Will and Pinnerは、(Willの研究に基づいて)これまでのauthenticityの議論を6つに分類している。(1) テクストの…、(2) テクストの受容の…、(3) 実世界との対応の…、(4) 教室の…、(5) 個人の振る舞いにおける…、(6) 文化的…。次いで、authenticityの政治的側面が取り上げられ、日本の英会話学校の広告が批判されているのはこの側面。そこでauthenticityの本質主義的概念と実存主義的概念が導入され、サルトルやハイデガーを引きつつ、哲学的概念としてのauthenticityが検討される。
13.09.2023 15:30 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
さしあたりKramsch先生の前書きと、Will and Pinnerの第1章を読んだが、これだけでも引き取って考えるべきこと盛り沢山で頭が満腹だ。
(白人の)英語母語話者講師とバイリンガルの日本語話者講師とフィリピン人講師に値段の差をつけてアピールする日本の英会話学校の広告が取り上げられて、(企業名を"SenseiSabetsu"と言い換えた上で)痛烈に批判されていた。
13.09.2023 15:29 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
EuroSLAで30%程度の値段で売っていたのでいくつか文献をゲットしてきたのだが、これは読書会をしてもよいと思う。「"authenticity"の意味が言う人によって様々」問題にいい加減マシな整理を与えたい。>Will, L., Stadler, W., & Eloff, I. (Eds.). (2022). Authenticity across languages and cultures: Themes of identity in foreign language teaching and learning. Multilingual Matters. amzn.to/45VPv6Q
13.09.2023 15:29 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
あと、途中の内容からすれば、やはり
伊藤 亜紗 (2022).『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』文藝春秋. amzn.to/3RhY2wc
には言及あって然るべき。
13.09.2023 07:39 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
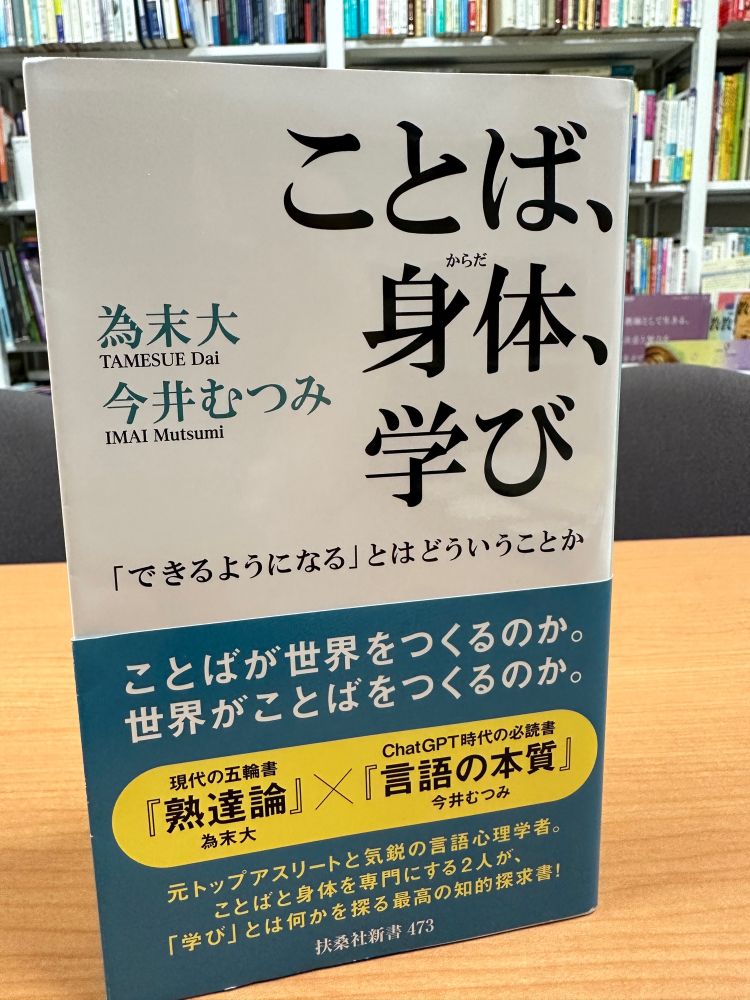
為末さんの言語化が明晰で、面白かった。引き合いに出される研究に今井先生色の強さはあるが、全体としては悪くない文献。
ただ、典拠を次々挙げるようなタイプの文献ではないことは承知しているけども、「これを私は『足場かけ』と呼んでいます」(p. 197)なんて辺りは、(先人に払うべき敬意の問題も含めて)おいおい大丈夫かよと思ってしまう。
『言語の本質』の宣伝期ということはあるにせよ、kotoba(2023秋号)の記事でも今井先生は「接地している」をのべつまくなしに、ゆるく使いすぎで勝手にちょっと心配だ。既に、「有意味学習」なんかの古い酒を新しい瓶に詰め替えただけの言葉になっているきらいが否めない。
13.09.2023 07:38 — 👍 2 🔁 2 💬 1 📌 0
かようにして、「英語の」や「何ができる」について各論者が自身の実践や信念であれこれ語る一方で、(特に小中高の)「教室」に対する解像度の粗さから、質疑応答・意見交換では、20年ぐらい前にとっくに通り過ぎたような話が展開されていて、掲げられているタイトルの輪郭と切実さに比して、残念に思った。
>ことばのまなび工房(監修)・若林茂則(編) (2023).『英語の教室で何ができるか』開拓社. amzn.to/3sT2dVa
13.09.2023 07:29 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
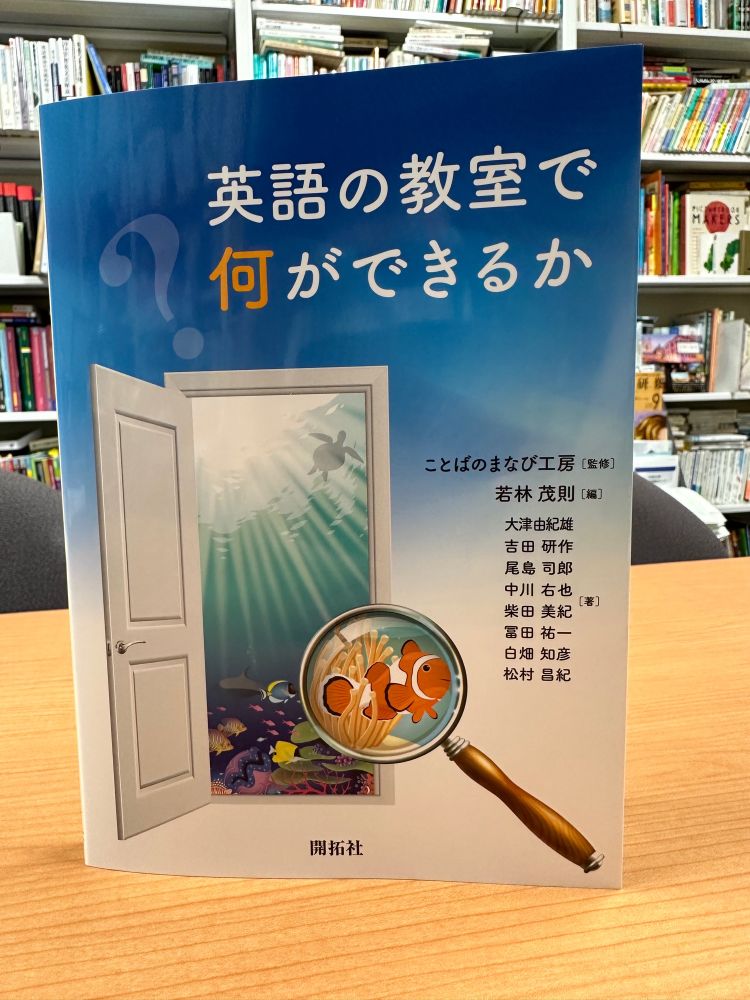
いただきもの。大津さん以外はタイトルに正面から答えきっていないように思った。至近要因として何をしなければならないかを語ってはいけないということはないが、「教室で何ができるか」はそれに尽くされるものではないだろう(難しく言えば、各自「教室で何ができるか」という問いの投射範囲を見誤っていないかという問題)。
松村さんの主張には理論的整理として賛同する部分が多いものの、やはり「教室で」の部分が弱いと感じる。そこを意外と(と言ったら失礼だけど)引き取ろうとしているのは白畑先生だが、教師の力量・問いかけが重要というのはSLAの知見に寄らずとも、今まで実践的に散々言い尽くされてきたことのように思われる。
13.09.2023 07:28 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0

サクサク読めることもあって、ビジネスって大変だなあと他人事のように流してしまったところもあるが、研究プロジェクトや行政とのお仕事にも当てはまること少なからずで随所噛み締めた。
>尾花山 和哉・株式会社ホクソエム(編) (2023).『データ分析失敗事例集: 失敗から学び、成功を手にする』共立出版. amzn.to/3YGzezJ
18.08.2023 02:19 — 👍 4 🔁 3 💬 0 📌 0

先日読んだ『思考の技術論: 自分の頭で「正しく考える」』で言及されていて、そういや読んでないなと移動中の読書。なるほど発刊からもう20年経つが、『思考の技術論』と繋がる。
具体例がいつもの如く面白く、論文の書き方を説く文献ではそんなにこってり語らないよというぐらい紙幅を割いて語られている。マニュアル的な使い方には向かないが、それがいい。
4年の卒論課題のために、あるいは秋学期のゼミで3年生に参考文献として紹介してあげたい部分がいくつか。
>鹿島 茂 (2003).『勝つための論文の書き方』文藝春秋. amzn.to/4579H5a
14.08.2023 14:03 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

半数の著者の個別の論考は読んだことがあったが、「ナチュラル・ペダゴジー」に関する文献をまともに読んだのは初めて。NP理論に対する批判も含め、様々な角度からの検討を読めて良かった。
>安藤 寿康(編) (2023).『教育の起源を探る: 進化と文化の視点から』ちとせプレス. https://amzn.to/45iiOj3
07.08.2023 03:48 — 👍 2 🔁 1 💬 0 📌 0

とても良いシリーズのとても良い本。特に第2章まで、語学の目的や文化の捉え方については、英語教育界隈の議論で目にすることはなく、それ故に英語教師の口から語られることも少ないであろう、それだけに英語教師やそれを目指す学生たちに読んでほしい文章だ。
ちょうど翻訳の仕事をしているので、後半のやや専門的な翻訳の話は、説教を受けている気持ちになって心の中で正座しながら読みました。おっしゃる通りで心洗われた。
>奈倉 有里 (2023).『ことばの白地図を歩く: 翻訳と魔法のあいだ』創元社. https://amzn.to/452UPVy
06.08.2023 03:51 — 👍 4 🔁 2 💬 0 📌 0
全体として、副題にある「貧困・校内暴力・いじめから、不登校・発達障害問題」といった切り口から子どもたちの「排除・周縁化」を描き出そうとした戦後教育史なので、好みは分かれそうだし、個々の記述に疑問を持つこともあるだろう。そういう評価ができることが一つの達成とも言えるので、教職課程の学生は独力で読み通すのはややハードルが高いかもしれないが、授業で批判的に取り上げてくれると嬉しい。
05.08.2023 13:44 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0

淡々とした文章でそれほど読みやすいとは言えないが、教科書的な通史程度では出てこない関係者の名前や当時の教師・子どもの声など、経緯や事情が比較的詳しく書かれており、教育学を学ぶ者は一読して損はしない。数字や引用も豊富。たとえば教科書採択の広域化のくだり(pp. 97−98)などは、広域採択制自体は知っていても、種類数の変遷のデータと併せて素直になるほどなと思った。
>小国 喜弘 (2023).『戦後教育史: 貧困・校内暴力・いじめから、不登校・発達障害問題まで』中央公論新社. https://amzn.to/3Qsbg9b
05.08.2023 13:44 — 👍 1 🔁 2 💬 1 📌 0

ちょっと前にテッド・チャンとアンディー・ウィアーを混同したまま彼らの小説と映画について話をすることがあって、あとで混同に気づいて「『メッセージ』は良い映画にせよ、私は小説はアンディー・ウィアーのほうが好きなのにテッド・チャン大好きみたいな話し方をしてしまった...」と後悔したのだが、つい先日文庫版が出た『息吹』を手に取ってみると、嗚呼テッド・チャンすごいわと思った。冒頭の作品だけでもその辺の長編にはない深みを味わえる。
>テッド・チャン(大森望(訳))『息吹』早川書房. https://amzn.to/43Z0gTM
05.08.2023 10:15 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
第23〜25章はそれまでの流れと性格が異なり、学生時代に論理学の文献に浸りすぎたせいかカットしてもいい気がしたが、ビジネスの戦略ストーリーに研究テーマの選択や論文の書き方を重ねる第20〜22章も研究者にとってはすこぶる示唆的で、科研等のプロジェクトについて自身に重ねながら読んでしまった。
とまとめて感じるのが、他の誰にこれが書ける?!という驚嘆と畏怖の念。贅沢な574ページだ。
05.08.2023 10:01 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
(第8章で既に『『パサージュ論』熟読玩味』のエッセンスが登場するが)ここまでに著者のこれまでの著作のエッセンスが惜しみなく開陳されているのも嬉しいところ。個人的には、第15章までのロジックが咀嚼できれば修士課程は合格、第16章から第19章までが博士課程から研究者として独り立ちするぐらいまでの段階で持てればうれしい見晴らし、という感覚を持った。
05.08.2023 10:00 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
特に二元論(的思考)の有り難みからy = ax の一次関数までが「正しく考える」方法としてつなげて整理できることに感動すら覚えた。第10、11章までを学生が読めば、卒論の問題設定や考察に大いに役立つことだろう。
具体例の理解に背景知識も求められる第12章以降はやや難易度が高い。しかし、ブロック『比較史の方法』から入り、家族人類学の系譜を経て、トッドの仕事を詳しく解説し、吉本隆明の「共同幻想論」のエッセンスを取り出した上で、ヘーゲル的弁証法を論じる第19章までは本書の白眉。
05.08.2023 09:59 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0

堂々と自立する574ページ。卒論から研究者人生まで、という感じでお腹いっぱいだ。もちろん幸福な満腹感。
前半、デカルト『方法序説』の4原則の詳細な読み解きから始まり、コンディヤックの『論理学』が並置され、なかなか読みあぐねるかもしれない。しかし、そこをくぐり抜けると抜群に面白く、前半の検討が必要なものだったことも実感できる。
>鹿島 茂 (2023).『思考の技術論: 自分の頭で「正しく考える」』平凡社. amzn.to/45hKGDS
05.08.2023 09:59 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0
教員研修の「三面騒議法」(模造紙と付箋のワークショップ)は、全部が全部ダメとはもちろん思わないが、もうそろそろいいんじゃない?と思ったりするところもあるので、現状の課題についても深掘りしてくれるといいとは思ったけど、学生には広く薦められる。
02.08.2023 04:52 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
北村紗衣です。北海道生まれ、駒場にいたあとロンドンでジェダイとなって戻ってきました。シェイクスピアリアンで、バーレスク好きです。
1913年創業の総合出版社です。2023年5月開始。
Iwanami Shoten, Publishers.
国産ギター好き(Ibanez, Fujigen, Tokai, Headway, Yamaha, etc.)🎸ギターを弾いている方の投稿を拝見しています(無言フォロー失礼します)
編集者@岩波書店。言語学・認知科学・数学の書籍や月刊誌『科学』(2022年6月号~2023年12月号では編集長)を担当しています。
企画・編集した書籍・雑誌: https://booklog.jp/users/hamakado
言語学の研究者(分散形態論、生成統語論、日本語学)、大学教員(筑波大学)/このアカウントでの発言は私が関わるいかなる組織の意見・見解も代表するものではありません
心理学をお仕事としている58歳。専門は社会心理学(説得・社会的認知など)だと思います。
English for Specific Purposes, tennis, rice growing, nature, traveling, kintsugi, dogs & cats, nojiri & miyota, #御代田 #里山保全 #ミニチュアシュナウザー
勉強嫌いの研究者(心理・教育)。酒も音楽も好きだ。メジャーどころが苦手な判官びいきだ。九州(熊本)生まれ金沢在住ののラテン系。モットーは「軽率は力なり」
専修大学人間科学部心理学科教授 学習心理学、動物心理学 Department of psychology, Senshu University. associative learning, animal cognition
北の大地で文章の書き方を教えつつ言葉(特に音声)のしくみを研究しています。近著は『日本語パラグラフ・ライティング入門』(研究社)
普通・中型免許(中型車は8tに限る)/ 集団ストーカーされていません / ゴールドカード(私学メンバーズカード) /ChatGPT課金 / D◯合 / 博士(人間科学)/ 18↑ / お金配らないおじさん
Junior Associate Professer, science education 教科教育学の研究をしています。専門は理科教育学です。「科学と教育」をテーマに色々と考えています。
英語教育2.0 Podcast https://anfieldroad.substack.com/about
社会的文脈における意思決定を専門とする適応論的社会心理学者。国境なき犬もふ団団長。
近刊: 『進化心理学概説』(ミネルヴァ書房)
https://www.minervashobo.co.jp/book/b673216.html
ちょっと前の仕事: 『不平等の進化的起源』(大月書店) 監訳
https://amzn.asia/d/a87QMBB
J.S.A. ワイン検定ブロンズ (2024)
J.S.A. ワイン検定シルバー (2025)
J.S.A. ワインエキスパート勉強中
Associate Professor, Faculty of Education, Chiba University / Visiting Scientist, RIKEN AIP
浦野研です。札幌の私立大学で英語を教えています。
https://www.twitter.com/uranoken
https://www.instagram.com/uranoken/
https://www.threads.net/@uranoken
https://mstdn.jp/@uranoken